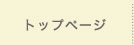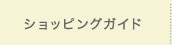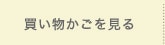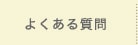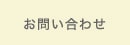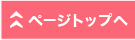第31回 犬猫に寄生するダニ。ニキビダニ。
滝田雄磨 獣医師
-
今回は、犬猫に寄生するダニのうち、
皮膚疾患を起こすニキビダニについてお話します。
-


-
ニキビダニは他のダニと比べると、とても細長い形状をしています。
大きさは小さく、毛包虫とも呼ばれるように、
主に毛穴の中に寄生します。そのため、飼い主が肉眼でニキビダニを発見して来院されることはありません。
重度感染による皮膚炎を主訴に来院されます。
-


-
ニキビダニの大きな特徴のひとつに、
常在しているという点があります。
常在とは、健康な犬猫にも常に存在しているという意味です。 したがって、ニキビダニが検出=異常ではありません。
過剰に増殖し、皮膚炎などの症状が出て初めて
問題となります。 -

生まれたばかりの新生子にニキビダニの寄生は見られませんが、
生後数時間で母犬から感染します。
人間においても常在しており、特に皮脂腺が発達している顔面には高密度で寄生しています。
そのことから、俗にカオダニとも呼ばれます。

ニキビダニは、寄生できる対象動物や部位が、種によって限定されています。
犬に寄生しているニキビダニが、猫に寄生することはありません。
同じく人間に寄生しているニキビダニが、犬猫に寄生することはありません。
さらに人間にいたっては、皮脂腺の浅いところと深いところとで、別の種類のニキビダニが寄生しています。
したがって、飼っている犬猫がニキビダニ症だと診断されたとしても、感染が種を越えて蔓延することはありません。

-
ニキビダニは、卵→幼虫→前若虫→若虫→成虫→産卵というサイクルで成長します。
孵化した幼虫が3回脱皮をして成虫になるのです。
このサイクルは15~30日、2~4週間で一周します。
幼虫、前若虫は運動能力が低く、感染能力も低いと考えられています。一方、成虫は運動能力が高く、湿潤などの環境が整うと、活発に移動します。
グルーミング時に口に入った成虫が、唾液腺開口部から侵入し、唾液腺内部から検出されたというケースも報告されています。 -


-
ニキビダニ症と診断されるとき、症状として、脱毛や皮膚炎などが認められます。
痒みに関しては、傷ができるほど掻きむしってしまう子から、全く痒がらない子まで様々です。
毛包虫ともよばれるように、ニキビダニは毛包を好んで寄生します。 -

そのため、発赤や色素沈着などの症状も、最初は毛穴の部位に認められます。
皮膚炎が悪化すると、苔のように皮膚が分厚くなったり、出血をともなったり、
腫れ上がったりします。

先述したように、ニキビダニは健康な子にもみられる寄生虫です。
それでは、ニキビダニ症を発症する子としない子との違いはどこにあるのでしょうか。
-
●若年発症性ニキビダニ症
生後18ヶ月(1才半)以内に発症した場合、若年性と称します。
幼若であるための未熟な免疫力が原因です。
多くの場合は、毛包洗浄効果を期待したシャンプー治療で軽快します。
ときに、無治療でも軽快することがあります。 -
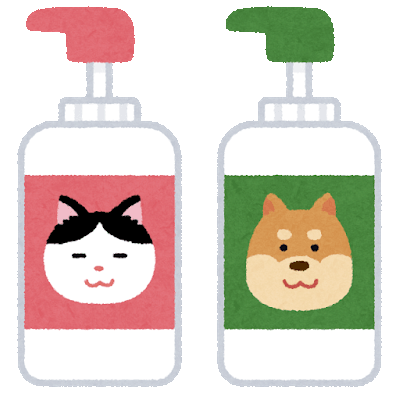
●成犬発症性ニキビダニ症
成犬後に発症した場合、成犬性と称します。
この場合、なんらかの原因により、免疫力が低下していることを考えなくてはなりません。
免疫力が低下する原因としては、免疫抑制剤の投与、内分泌疾患(クッシング症候群、甲状腺機能低下症など)、栄養不良、ストレス、発情、その他全身性の疾患が挙げられます。
-
成犬性の場合、重症化することが多く、駆虫薬の投与と同時に基礎疾患をみつけて治療する必要があります。
基礎疾患が不明の場合は、定期的な駆虫薬によるコントロールが望まれます。 -
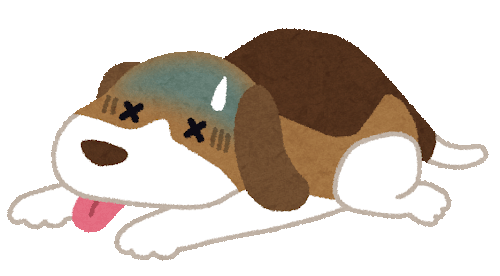

●駆虫薬
ニキビダニは、ダニではあるものの、残念ながら一般的なノミ・ダニ駆虫薬では駆虫することが出来ません。
むしろ、一般的な駆虫薬のなかには、ニキビダニの駆虫薬投与との併用が禁忌であるものもあるため、注意が必要です。
(スピノサドと高用量イベルメクチン、ドラメクチンなど)
-
ニキビダニ症に使われる駆虫薬には、内服、注射、外用、薬浴など様々なものがあります。
その中でも、近年開発された3ヶ月持続するタイプの経口薬が、
ニキビダニに有効性があると注目されています。 -

●二次感染のコントロール
ニキビダニ症とともに、細菌などの感染症を併発することが多くあります。
その場合、感染症を全て治療しないと、皮膚の症状を抑えることが出来ません。
他に感染症が隠れていないか、しっかり検査をして治療することが大切です。
●基礎疾患の治療
主に成犬性ですが、
ニキビダニ症を発症する原因となる基礎疾患の存在を考えなくてはなりません。
基礎疾患となりうる疾患は多岐にわたりますが、全身検査をし、基礎疾患を見つけださないと、治療はなかなか奏効しません。
高齢の場合は、積極的に全身検査を受けましょう。

-
猫のニキビダニ症は、犬と比べると希な疾患です。
症状としては脱毛、発赤、カサブタなどですが、他の疾患との鑑別が困難なことがあります。
発症してしまった場合の基礎疾患としては、ウイルス感染(猫エイズなど)、糖尿病、内分泌疾患(甲状腺機能亢進症など)、自己免疫性疾患、腫瘍などがあげられます。
治療法としては、週1回の駆虫薬の注射や、薬浴が選択されます。 -


-
われわれ人間の顔にも常在しているニキビダニ。
そういった意味では、もっとも身近なダニとも言えます。
ニキビダニが検出されたから全てニキビダニ症というわけではありません。
しかし、ニキビダニの大量増殖を認めたら、そこから基礎疾患の検討、検査へと進むことができます。
脱毛、発赤などの異常が認められたら、積極的に受診し、検査を受けるようにしましょう。 -